ココロとカラダのコラム0031:足三里穴の効用
←前の記事 次の記事→
経穴(ツボ)には非常にマイナーなものから非常にポピュラーなものまで、たくさんのものがあるが、足三里は万能穴とも呼ばれ、最もよく使われるツボの1つ。松尾芭蕉が『奥の細道』の冒頭で
「道祖神のまねきにあひて、取(とる)もの手につかず。もゝ引の破(やぶれ)をつゞり、笠の緒付かえて、三里に灸すゆるより…」
と、旅に出る準備として足三里にお灸をしたと書いているように、鍼灸院の中には患者の主訴が何であれ必ず足三里には鍼を打つ、というところもあるくらいだ。
経絡では胃経に属し、取穴は膝蓋骨(膝の皿)の下縁から4横指(経絡的には3寸)下で、脛骨の外縁にある。
ツボの作用を決める要素はいくつかあって、まずはツボの場所、そしてどの経絡に属するかということがある。足三里は膝周りにあるので膝に関する疾患(例えば膝痛など)に使えるし、胃経に属するので胃を含む消化器系の症状(例えば胃痛、胸焼けなど)に対する作用を持っている。
実は胃痛や胸焼けは胃酸が出すぎる場合にも出なさ過ぎる場合にも起こる。ただ、どちらの場合も本人の自覚症状は同じなので、胃酸が出すぎることでそうした症状が出ているのに胃酸の分泌を高める薬を使ってしまったり、逆に胃酸が出なさ過ぎるのに更に胃酸の分泌を抑えてしまう薬を飲んで、より一層症状を悪化させてしまうことがしばしばある。
では、足三里を刺激すると胃酸の分泌はどうなるのだろうか? それについては既に研究結果が出ていて、胃酸の分泌は盛んになる場合と抑えられる場合の両方があることがわかっている。「え、何それ?」と思われたかもしれないが、足三里を刺激すると胃酸が過剰に分泌されている場合はそれを抑えるように、また胃酸があまり分泌されていない場合はそれを促進するように、体が反応するのである。
こうしたことは足三里に限った話ではなく多くのツボで同じことが言えるが、ツボには何かの働きを強める作用も弱める作用もあるのだ。もう少し正確に言えば、
ツボとは、体のある部分の働きが亢進していたり低下していたりするのを中庸に戻す作用がある
のである。
足三里の話に戻ると、それが属する胃経は経絡として歯や顔面部にも流注(るちゅう)している。そのため、足三里は歯痛や顔面の様々な疾患(例えば鼻づまり、耳鳴り、視覚異常など)にも用いられる。
また経穴学ではツボには五行穴、八会穴、四総穴、八総穴といった要穴のグループがあるのだが、足三里は五行穴の中の胃の合穴に当たる。合穴とは経脈の入るところとされ、そこからも足三里が生体エネルギーである「気」に対する強力な作用を持っていることがわかる。足三里が全身調整穴として使われる理由の1つが、そこにある。
そうしたことを知った上で、足三里をご活用いただきたい。
関連コラム コラム0002:経絡経穴の反応を読む コラム0009:三陰交穴の効用

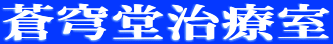
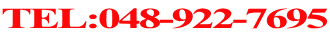

埼玉県草加市、川口市、八潮市、越谷市、東京都足立区千住、竹ノ塚の心身統合治療室
キネシオロジー(カイロプラクティック)、クラニオセイクラル・ワーク(クラニオ)、鍼灸(はりきゅう)、メディカル・アロマテラピー、フォーカシング、波動療法の総合整体治療院
蒼穹堂治療室(そうきゅうどうちりょうしつ)のホームページ
蒼穹堂治療室トップページへ
