ココロとカラダのコラム0072:東洋医学から見ためまい
←前の記事 次の記事→
西洋医学的にはめまいは大きく分けて、自分の周囲がグルグル回るように感じる回転性のめまい、立ち上がった時に急に目の前が暗くなった感じがして倒れそうになる起立性のめまい(起立性循環調節障害)、フラフラする/クラクラするようなめまい、があると考える。
めまいを起こす疾患は非常に多く、めまいだけでは原因を探るのは難しいが、回転性のめまいは主に体の平衡覚を司る前庭神経の障害、起立性循環調節障害はその名の通り循環器系の問題、フラつくようなめまいは小脳や脊髄の失調の可能性を一応疑う。
では、東洋医学(中医学)的な切り口でめまいを考えるとどうなるかというと、例えば次のような可能性が挙げられる。
なお、以下に肝や腎などの言葉が出てくるが、中医学における肝、腎、血(けつ)などは西洋医学的な解剖学における肝臓、腎臓、血液とは必ずしも一致しないので念のため。
・(肝の)気が頭方に上がってしまっていることによって起こるめまい。随伴症状としては頭痛、頭張、耳鳴り、怒りっぽいなどの情緒不安定、不眠などがある。
(肝の臓は、感情では怒りやイライラなどに対応する。)
・気や血が不足して体が弱ることによって起こるめまい。随伴症状には動悸、息切れ、肩こり、食欲不振、疲労感、不眠、顔色の悪さなどがある。
・腎が弱り、精を貯蔵できなくなることで起こるめまい。随伴症状には体のダルさ、頭がボーッとした感じ、記憶力の減退、抜け毛が増える、歯が弱くなる、筋力低下、腰や膝が鈍く痛む、体の冷えなどがある。
(精は気=生体エネルギーの原料となるもの。)
・気・血・水(すい)のうちの水の流れが滞ることによって起こるめまい。随伴症状には頭重感、胸腹部の不快感、吐き気、嘔吐、食欲不振などがある。
西洋医学的な分類と中医学的な分類の大きな違いは、前者が症状の違いに基づいて分類しているのに対して、後者は人の身体が取り得る状態をベースに、めまいを引き起こす可能性のあるものをピックアップしている点にある。
中医学では「同病異治・異病同治」という考え方がある。「見かけの上での症状は同じでも病として異なるものがあるので、それについては治療法を変えなければならない。また見かけの上では異なる症状でも病としては同じものもあり、それについては同じ治療法が使える」という意味である。
更に言うと、中医学では原因がわかれば治療法が一元的に定まる(これを「診断即治療」という)。上の例では、例えば(肝の)気が頭方に上がってしまうことによって起こるめまいなら、肝気を足方へと下げるような施術をすればよいのだ。
関連コラム コラム0033:五行(ごぎょう)システム コラム0051:臓腑の時間

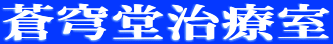
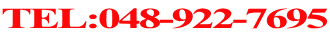

埼玉県草加市、川口市、八潮市、越谷市、東京都足立区千住、竹ノ塚の心身統合治療室
キネシオロジー(カイロプラクティック)、クラニオセイクラル・ワーク(クラニオ)、鍼灸(はりきゅう)、メディカル・アロマテラピー、フォーカシング、波動療法の総合整体治療院
蒼穹堂治療室(そうきゅうどうちりょうしつ)のホームページ
蒼穹堂治療室トップページへ
