ココロとカラダのコラム0073:手技療法で肝臓を調べる
←前の記事 次の記事→
最近、太ってもいないし酒も飲まないのに脂肪肝になっている、という「隠れ脂肪肝」が一部で問題になっている。
ちなみに脂肪肝とは、肝臓の細胞の中に中性脂肪が沈着しているもので、この状態を放置していると、死んだ肝細胞が線維に置き換えられていく線維化を経て、肝硬変、更には肝臓癌へと移行する可能性がある。自覚症状はあまりなく、気づいた時には手遅れだったということも少なくない。
病院など医療機関で肝臓を調べる場合は、血液検査、超音波エコー、CT/MRIなどが用いられるが、医療機関ではない整体、鍼灸など各種療法の治療院では、当然のことながらこんな方法は使えない(設備もないし何より法律的に許されていない)。それでも、肝臓の状態を調べることはできないのかというと、決してそんなことはない。
以下、私のところで用いている検査法をいくつか紹介しよう。
まずはキネシオロジーによる検査。
筋反射テストでは、体の悪い部分、何らかのケアが必要な部分に触れると筋力が弱くなる、という性質がある。なので肝臓付近に手を触れた状態で筋反射テストを行う。
それ以外にも、各臓器は特定の筋肉と対応していて臓器の異常は対応する筋肉の異常として現れる、という「内臓筋肉反射」の機序を用いた検査もある(なお、肝臓に対応する筋肉は大胸筋の胸肋部)。
次に内臓の自動性を調べる検査。
これは主に内臓マニピュレーションで使う方法だが、各臓器はそれぞれ非常に微細ではあるが固有の周期的な動き(これを自動性という)を持っている。肝臓を例に取ると、肝臓は大きくひしゃげたラグビーボールのような形をしていて、その長軸を回旋軸とする周期的な内方、外方への回旋を行っている。ところが、その臓器に異常が生じると内方、外方への回旋が均等でなくなったり、回旋の動きが消えてしまったり、回旋ではない例えば振り子運動のようなものが現れたりする。
内臓マニピュレーションでは、この自動性を軽く皮膚に触れた手で触知するのだが、クラニオ(頭蓋仙骨療法)で頭蓋から間接的に知覚する方法もある。
最後に東洋医学(中医学)的な検査法。本当のことをいえば、中医学でいう肝の臓と西洋医学的な意味の肝臓とは別物なのだが、経験的に肝臓の異常は肝の臓の異常として検出できることが多い。
検査法にはいくつかあるが、有名なところでは脈診。六部上位脈診という方法を使い、肝の臓に相当する部分の脈状を調べる。肝に異常があると弦脈という特徴的な脈が現れる。また脈診以外にも、脇腹が張って痛い(胸脇苦満)といった愁訴や肝経ラインの反応などから肝の状態を推し量ることができるのだ。
関連コラム コラム0037:心臓疾患のサインは広範囲に現れる コラム0041:簡単に動脈硬化かどうかわかる法

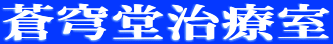
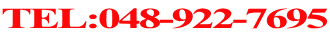

埼玉県草加市、川口市、八潮市、越谷市、東京都足立区千住、竹ノ塚の心身統合治療室
キネシオロジー(カイロプラクティック)、クラニオセイクラル・ワーク(クラニオ)、鍼灸(はりきゅう)、メディカル・アロマテラピー、フォーカシング、波動療法の総合整体治療院
蒼穹堂治療室(そうきゅうどうちりょうしつ)のホームページ
蒼穹堂治療室トップページへ
